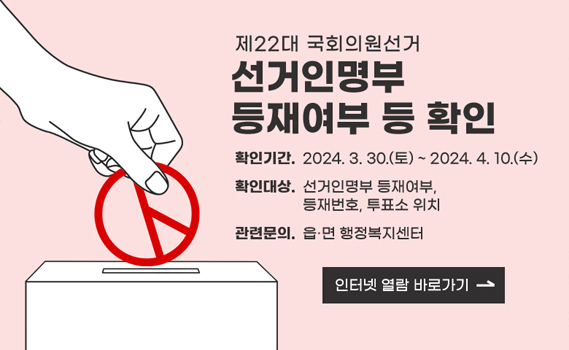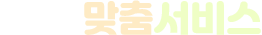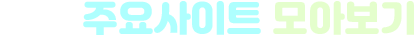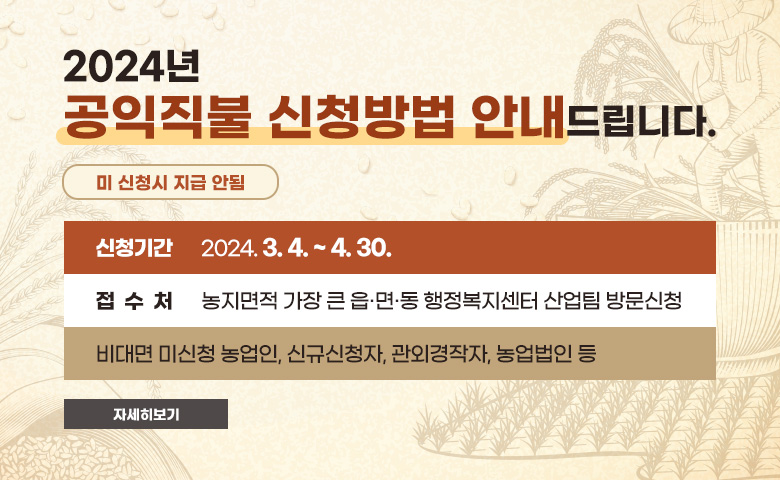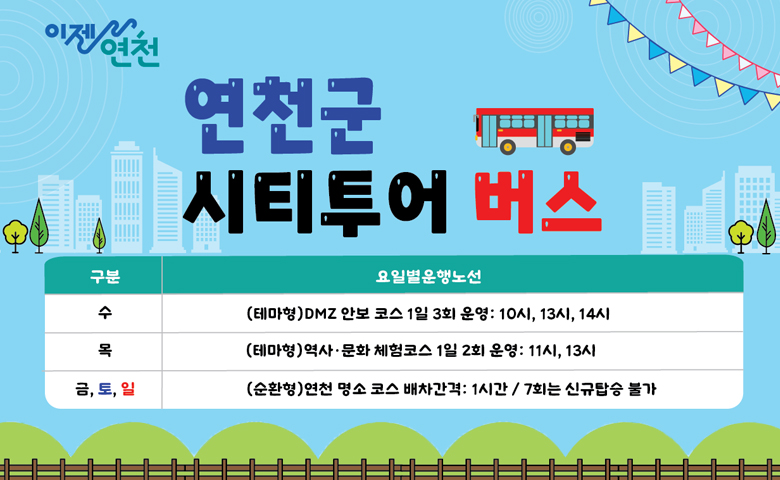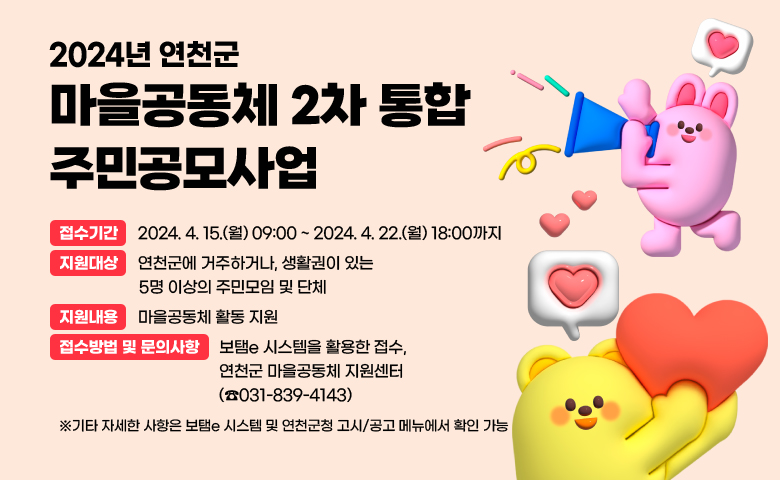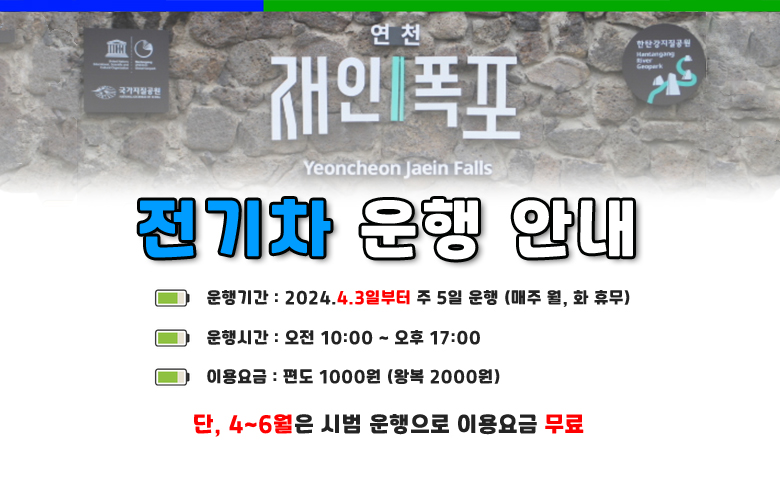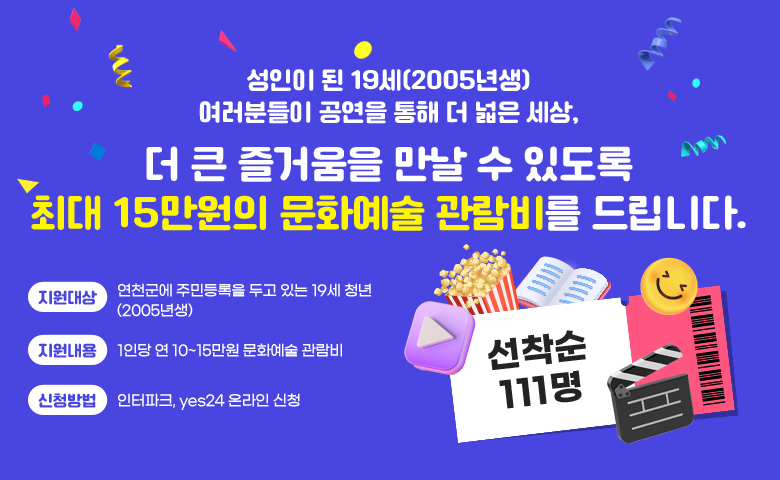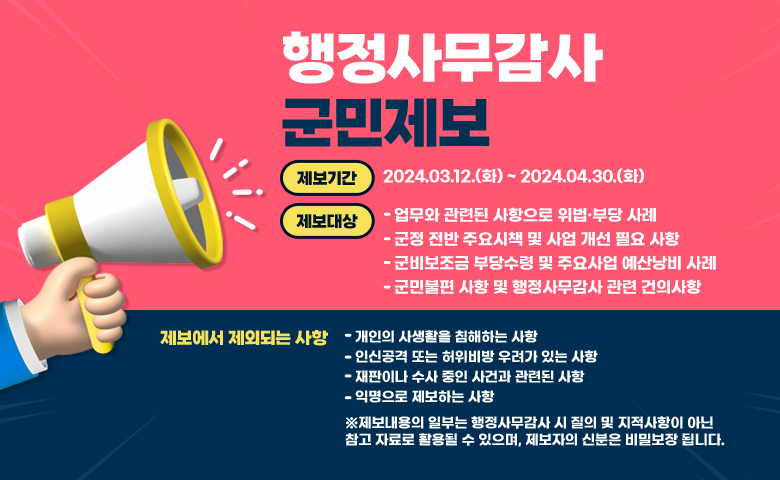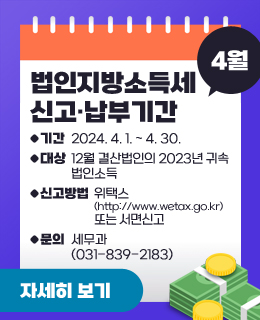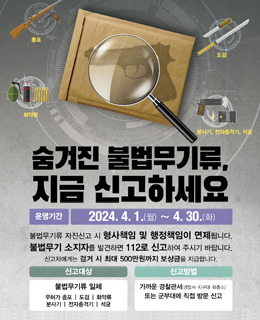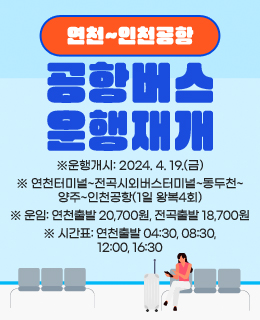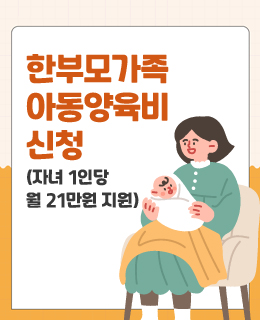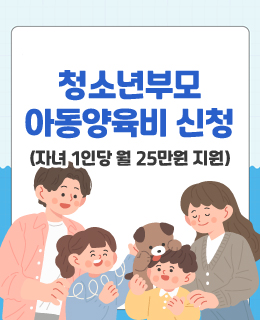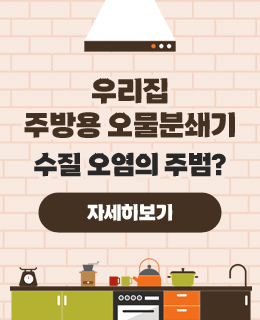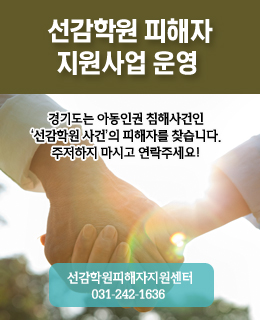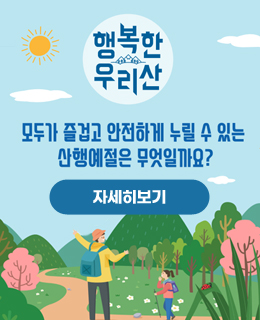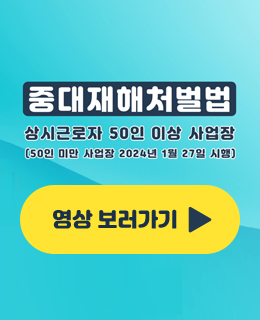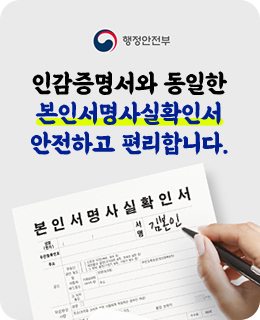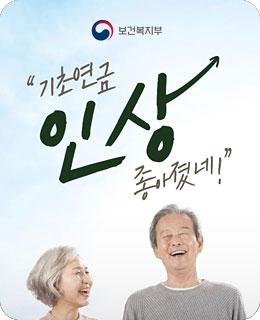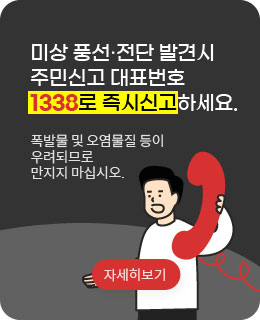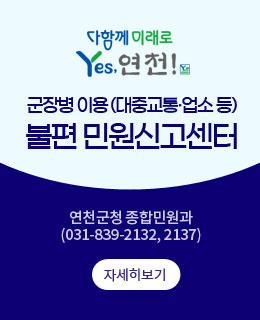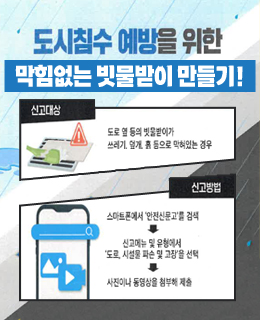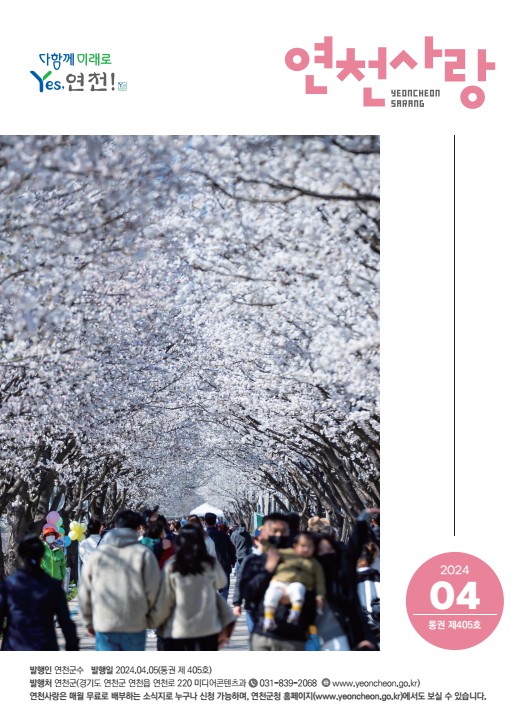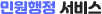지금연천은
주요소식
-
-
2024년 청년 이사비 및 중개보수비 지원 사업 안내드립니다
가. 신청일시 : 2024. 4. 8.(월) 10:00 ~ 5. 3.(금) 17:00 ※ 2차 공고 8월 예정 나. 지원대상 : 2024. 1. 1. 이후 경기도 전입 청년(19세~39세) 중 아래의 요건을 갖춘 자 - 경기도 내 거주 중인 무주택 청년 - ‘건강보험료 소득판정기준표’상 기준중위소득 120% 이하 - 거래금액 2억원 이하 전ㆍ월세 임차 - 주민등록등본의 세대주 및 임대차 계약서의 임차인: 청년 본인 다. 신청방법 : 온라인 신청(잡아바 어플라이 통합접수시스템) ※apply.jobaba.net 라. 모집인원 : 800명 마. 지원내용 : 이사비(운반비, 포장비) 및 중개보수비 지원(1인 최대 25만원) 바. 협조사항 - (시·군) 시·군·구 및 공공기관 홈페이지에 게시·홍보 - (공공기관 / 홍보기획관) 기관 홈페이지, SNS 게시 등 사업 홍보
지역경제과 2024.04.19 -
연천군 중면 탄소중립 도시 선포식 개최
우리군 탄소중립 사회로의 이행을 위한 본격적인 시작을 알리고자 아래와 같이 '중면 탄소중립 도시 선포식'을 진행합니다. ▣ 행사명: 중면 탄소중립 도시 선포식 ▣ 행사장: 중면 삼곶리 422 댑싸리 공원 ▣ 행사일: 2024년 4월 24일(수) 16:00~17:30 ▣ 참여대상: 연천군민 누구나 많은분들이 참석 하셔서 희망찬 시작을 함께 해주시기 바랍니다.
환경보호과 2024.04.18 -
‘24년 기후변화주간(4.22~4.28) : #우리의 탄(소중립)생(활실천), 오히려 좋아! :
#우리의 탄(소중립)생(활실천), 오히려 좋아! * 탄소중립 생활 실천이 불편하게 생각될 수 있지만, 지구를 위하고 탄소중립 포인트 혜택으로 돌아온다는 ‘기대와 다른’ 긍정적인 일임을 의미 ▣ 지구의 날 54주년을 맞아 기후위기와 탄소중립에 대한 인식 제고 및 실천행동 확산을 위해 4월 22일부터 28일까지 기후변화주간이 운영됩니다. ○ 연천군 중면 탄소중립 도시 선포식 개최 - 행사일시: 2024.4.24.(수) 16:00~17:30 - 행사장소: 연천중 중면 댑싸리 공원 ○ 기후변화주간 전용 웹페이지(https://www.gihoo.or.kr/earthday2024/ - 이벤트를 통한 카카오톡 이모티콘 증정(4.22~) - 탄소중립 실천포털 이벤트 참여(4.23.~5.13.): 문화상품권 증정 ○ 탄소중립 실천포인트제(https://www.cpoint.or.kr/netzero/main.do)에 가입하셔서 환경도 지키고 포인트도 받으세요. ○ 탄소중립 포인트제(에너지)(https://cpoint.or.kr/) 에 가입하신 후 전기, 수도, 가스량을 절약하시면 현금(또는 그린캐쉬백)으로 혜택을 돌려드립니다. ○ 제54주년 지구의 날 소등행사 추진 - 행사일시: 4월 22일(월) 20:00~20:10(10분)간 - 행사대상: 공공기관 및 공동주택(300세대 이상) 3개소(전곡 세띠앙아파트, 전곡 코아루더클래스, 전곡 휴먼시아 1차 아파트) ○ 1일 차 없이 출근하기 - 출·퇴근거리 4km 이하인 직원은 도보, 자전거, 대중교통 이용 실천
환경보호과 2024.04.18 -
[연천군청년센터] 방과후 아동지도사 1급과정 수강생 모집합니다!!
방과후 아동지도사 1급과정 수강생 모집합니다!! 초등교육과정 맞는 방과 후 프로그램 운영 및 지도방법, 실습하고 자격증 취득까지!! 월요반 / 5.13~7.15 / 10:00~12:00 목요반 / 5.9 ~7.18 / 18:30~20:30 (신청자 많은 시간대로 1타임만 운영 예정) 20명 교육비는 무료 교재,교구,실습비 : 자부담 4만원 자격증 응시비용 : 자부담 만19~39세 연천군민,재직자,사업자 4.18~4.30까지 https://linktr.ee/yc_youth 링크누르고 방과후 아동지도사 신청해주세요 839-4142
지역경제과 2024.04.18 -
2024년도 농촌지도 시범사업 재공고(2차)
▸신청기간 : 2024. 4. 17.(목) ~ 2024. 4. 29.(월) ▸신청방법 : 연천군농업기술센터 해당 사업별 담당자 상담 후 신청서 제출 사업별담당자 이메일 또는 우편제출(신청접수 마감일 18시 도착분까지 인정) (※ 이메일, 우편제출의 경우 담당자와 전화 통화하여 접수여부 확인바람) ▸신청자격 : 연천군에 거주(주민등록)하는 농업인으로 최근3년간(2021∼2023) 농업기술센터에서 시행한 보조금 5백만원 이상의 시범사업을 하지 않은 농업인 단 단체, 단지사업과 마을단위 사업은 제외, 축사 등 무허가 건축물 지원 불가 ※ 신청인은 농업경영체 등록이 되어있어야 하고, 국세․지방세 체납이 없어야 함. * ( )는 1개소당 사업비입니다. 세대주명의 신청, 1세대당 1개 사업만 신청
농업개발과 2024.04.18
-
-
-
2024년 양성평등기금사업 "행복을 요리하는 아빠" 프로그램 참여자 모집 안내
2024년 양성평등기금사업 "행복을 요리하는 아빠" 프로그램 참여자를 모집합니다. - 모집기간: 2024. 4. 15(월) ~ 5. 10(금) - 모집대상: 30~60대 연천군 거주 남성 12명 - 교육기간: 5. 16. ~ 7. 30. (13:30~16:30)(매주 화요일 1회) - 교육내용: 성인지교육 1회, 요리실습 9회, 시연회 1회 - 교육장소: 연천군통일평생교육원
사회복지과 2024.04.19 -
28보병사단] '24년 1575부대 시설관리원 채용 인원 및 요건
1.. 시설안전관리 채용직위 : 시설안전관리 인 원 : 3명 담 당 직 무 : 1. 시설물 유지관리분야 ⦁부대 내 시설물 관리(토목, 기계설비, 전기, 보일러, 냉난방기, 부대관리 등) ⦁기타 현역인원 지원업무 근무지역 : 연천군 청산면 초성리 / 연천군 연천읍 현가리 2. 청소관리원 채용직위 : 청소관리원 인 원 : 3명 담당직무 : 군 공용시설 청소 근무지역 : 연천군 (군남면) ※ 성적순으로 채용예정인원 우선 채용/채용인원 3개월 이내 퇴직시 후순위자 채용 예정임. ※ 후순위에 있는 예정자는 합격자 미공고/채용인원 퇴직 시 별도 통보 * 첨부서류 다운받아 응시원서 작성 연천군일자리센터 문의 및 군 담당자 용명호 (031-820-6104)
지역경제과 2024.04.16 -
2024 제4차 연천군체육회 경기스포츠클럽 인턴 채용 공고
연천군체육회 경기스포츠클럽 인턴 채용 공고를 붙임과 같이 안내하오니 많은 지원 바랍니다.
문화체육과 2024.04.16 -
2024년도 제1회 신규인턴(청년인턴) 공개채용 공고
연천군시설관리공단 공고 제2024-26호 2024년도 제1회 신규직원(청년인턴) 공개채용 공고 연천군시설관리공단에서 근무할 청년인턴 채용계획을 다음과 같이 공고합니다. 2024년 4월 15일 연천군시설관리공단이사장
기획감사담당관 2024.04.16 -
바우처 개인택시 사업자 모집공고
연천군시설관리공단 공고 제2024-25호 2024년 연천군 바우처 개인택시 사업자 모집공고 연천군시설관리공단에서는 교통약자 이동지원을 위한 바우처 개인택시 사업자를 다음과 같은 모집합니다. 2024년 4월 15일 연천군시설관리공단 이사장
미디어콘텐츠과 2024.04.15
-
-
-
낙뢰 국민행동요령 안내
낙뢰 국민행동요령 게시합니다.
안전총괄과 2024.04.18 -
2024년 치유농업 프로그램 운영 농장 모집
연천군농업기술센터에서는 치유농업 활용 복지화 지원사업 추진에 따른 치유농업 프로그램 운영 농장을 다음과 같이 모집합니다. 1. 모집기간: 2024. 4. 15.(월) ~ 4. 19.(금) 2. 모집대상: 관내 치유농업 프로그램 운영가능 농장 4~6개소(변동가능) 3. 신청조건: 치유농업 관련 교육이수 농장(온,오프라인) 4. 신청방법: 이메일 접수(jiniatti@korea.kr) 또는 농업기술센터 농업개발과 방문접수 5. 제출서류: 참가신청서, 농장소개서, 프로그램 운영계획서, 개인정보 수집,이용,제공동의서 등 6. 제출 및 문의: 생활자원팀 안혜진 주무관(031-839-4246) 7. 사업개요: 첨부파일 참조 붙임 1. 모집공고문 1부. 2. 참가신청서 등 양식 각1부. 끝
농업개발과 2024.04.16 -
아동주거빈곤가구 클린서비스지원사업
1. 신청대상: 반지하, 옥탑 또는 최저주거 면적기준 이하의 주택 등에 거주하는 만18세 미만 아동가구 *면적기준: 4인가족 기준으로 43㎡이하, 반지하, 옥탑은 면적기준 없음 *소득기준: 중위소득 100%이하 또는 기초생활수급자 등 2. 신청기간: 2024. 1. 22.(월) ~4. 30.(화) 3. 신청방법: 주소지 행정복지센터 4. 지원내용: 가구당 300만원 이내 (클린서비스 및 물품지원)
복지정책과 2024.04.02 -
2024년 스마트축산 패키지 보급 공모사업 설명회 개최 알림
'24년 스마트축산 패키지 보급 공모사업 설명회 - 대상: 공모사업 참여를 희망하는 스마트축산 ICT장비 및 솔루션 업체 등 - 일시: '24. 4. 4. (목) 14:00 ~ 15:30 - 장소: 축산물품질평가원 세종홀(세종시 아름서길 21, 축산물품질평가원 본원 1층 세종홀(대강당)) ※ 설명회 관련 자세한 사항 붙임 참조 ※기타문의: 축산물품질평가원
축산과 2024.03.29 -
2024년 연천군 국화동호회 모집
가. 모집단체 : 연천군 국화동호회 나. 모집기간 : 2024. 3. 25. ~ 4. 5. (12일간) 다. 모집정원 : 20명(기초반 20명) ※ 전문반 별도 추진 라. 모집내용 : 국화재배 실습 교육 및 국화전시회 참여 마. 관련문의 : 농업개발과 과학영농팀 조명희(☎031-839-4238)
농업개발과 2024.03.26
-
-
-
건물번호 부여 개별고시
1. 아래의 고시공고를 [시군구보][홈페이지][게시판]에 게재하고자 합니다. 2. 「도로명주소법」 제7조제6항 및 같은 법 시행규칙 제12조제1항 규정에 따라 건물 등에 부여한 도로명주소를 다음과 같이 개별고시합니다. 가. 고 시 명: 건물번호 부여 개별고시 나. 고시기간: 2024. 4. 19. ~ 2024. 5. 2. (14일간) 다. 고시방법: 군게시판, 홈페이지, 군보 라. 고시내용: 건물번호 부여 4건 붙임 도로명주소 개별고시문 및 조서 1부. 끝.
종합민원과 2024.04.19 -
공시송달 공고연천IC 연결도로 개설공사)
1. 우리 군에서 시행하는 '연천IC 연결도로 개설공사'에 편입되는 토지 등에 대하여 소유자에게 보상 협의 요청공문을 송달하였으나, 2. 송달받을 자의 주소・거소 불명 등 기타 사유로 보상 협의가 불가능하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행령」제4조 및 「행정절차법」제14조 규정에 따라 붙임과 같이 공시송달 공고하고 게재하고자 합니다.
건설과 2024.04.19 -
하천점용허가 고시
「하천법」제33조제7항 및 같은 법 시행령 제38조 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다. 1. 하천의 명칭 : 임진강(국가하천) 2. 점용자 성명 : 서성하 3. 점용자 주소 : 경기도 연천군 백학면 청정로 53번길 121 4. 점용의 목적 : 토지점용(주차장 활용) 5. 점 용 위 치 : 경기도 연천군 백학면 노곡리 880-4외 2필지 6. 점 용 면 적 : 813㎡ 7. 허가의 유효기간 : 2024.04.17.~2028.12.31.
건설과 2024.04.18 -
2023년 연천군 고충처리위원회 운영상황 공표
「연천군 고충처리위원회 구성 및 운영에 관한 조례」 제27조 제1항에 따라 2023년 연천군 고충처리위원회 운영상황을 붙임과 같이 공표합니다. 1. 운영개요 2. 운영성과 3. 권고사항 등 내역 및 결과 붙임 2023년 연천군 고충처리위원회 운영상황 공표 1부. 끝.
기획감사담당관 2024.04.18 -
용역 소액수의 견적제출 안내공고[임진강 중류 제방 정밀안전점검 및 성능평가 용역]
1. 견적에 부치는 사항 가. 용 역 명: 임진강 중류 제방 정밀안전점검 및 성능평가 용역 나. 위 치: 연천군 백학면, 장남면 제방 일원 다. 용역기간: 착수일로부터 60일 라. 용역개요: 과업지시서 참조 마. 기초금액: 금60,926,000원(부가가치세 포함) 2. 현장설명: 없음(생략) 3. 견적제출 또는 개찰의 장소 및 일시 가. 견적서 접수개시일시: 2024.4.19.(금) 10:00 나. 견적서 접수마감일시: 2024.4.24.(수) 11:00 다. 견적서 개찰일시: 2024.4.24.(수) 11:00(사정에 따라 개찰시간이 지연될 수 있음) 라. 견적서 개찰장소: 연천군청 회계과 입찰집행관 PC 마. 본 견적제출은 전자입찰로 집행되며, 소액수의 견적제출 및 총액입찰입니다. 4. 견적제출 참가 자격 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 따른 자격을 갖추고, 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우 해당사업에 관한 사업자등록증이나 관련법령에 따른 허가・인가・면허・등록・신고 등 관련서류의 사업장 소재지)가 경기도에 소재한 업체로서, 아래의 자격을 모두 갖춘 자이어야 합니다. 가. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제28조 및 같은 법 시행령 제23조에 의한 안전진단전문기관(수리시설) 또는 안전진단전문기관(종합)으로 등록한 업체 나. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제9조에 의한 토목 또는 안전관리 분야의 건설기술인 중 특급기술인 이상으로, 국토교통부장관이 인정하는 정밀안전진단 및 성능평가교육(수리분야)을 이수하고 그 분야의 정밀안전점검 또는 정밀안전진단업무를 실제로 수행한 기간이 2년 이상인 자로 시설물통합정보관리체계에 등록된 책임기술자를 보유한 업체 ※ 책임기술자 자격요건: 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」(별표5) 참조 ※ 책임기술자 보유여부는 입찰공고일 기준으로 판단하며, 관련협회에서 발급한 기술자보유증명서 및 교육이수 수료증을 계약 체결 전에 제출하여야 하고, 미제출시 부적격 처리합니다. - 이하 내용은 공고문을 참고하시기 바랍니다.
회계과 2024.04.18
-
-
-
2024년 제1회 연천군 지방공무원 경력경쟁임용(국가유공자 특별채용)시험 최종합격자 공고
2024년 제1회 연천군 지방공무원 경력경쟁임용(국가유공자 특별채용)시험 최종합격자를 붙임과 같이 공고합니다. 2024년 3월 22일 연천군인사위원회위원장
행정담당관 2024.03.22 -
2024년 제1회 연천군 임기제공무원 임용시험 최종합격자 공고
2024년 제1회 연천군 임기제공무원 임용시험 최종합격자를 붙임과 같이 공고합니다. 2024년 3월 22일 연천군인사위원회위원장
행정담당관 2024.03.22 -
2024년 제1회 연천군 공무직 근로자 및 대체인력(기간제 근로자) 채용시험최종합격자 공고
2024년 제1회 연천군 공무직 근로자 및 대체인력(기간제 근로자) 채용시험최종합격자를 붙임과 같이 공고합니다.
행정담당관 2024.03.21 -
2024년 제1회 연천군 공무직 근로자 및 대체인력(기간제 근로자) 채용시험 1, 2차 전형 합격자 및 면접시험 계획 공고
2024년 제1회 연천군 공무직 근로자 및 대체인력(기간제 근로자) 채용시험 1, 2차 전형 합격자 및 면접시험 계획을 붙임과 같이 공고합니다.
행정담당관 2024.03.15 -
2024년 제1회 연천군 지방임기제공무원 임용시험 서류전형 합격자(재공고 포함) 및 면접시험 시행계획 공고
2024년도 제1회 연천군 지방임기제공무원 임용시험 서류전형 합격자(재공고 포함) 및 면접시험 시행계획을 붙임과 같이 공고합니다. 2024. 3. 13. 연천군인사위원회위원장
행정담당관 2024.03.13
-
-
-
2024년 연천군 어촌체험 안전가이드 채용모집공고
어촌체험마을 활성화를 지원하기 위하여 2024년 어촌체험 안전가이드를 아래와 같이 모집 공고하오니 관심있으신 분들의 많은 참여를 바랍니다. 1. 접수기간: 2024.04.19. ~ 2024.04.26. 2. 접수처: 연천군청 축산과 축수산팀(농업기술센터 내) 3. 접수방법: 방문접수 4. 모집인원: 1명 붙임 공고 1부. 신청서 1부. 끝.
축산과 2024.04.19 -
2024년 농업기술센터(농산물종합가공센터) 기간제근로자 채용 공고
농업기술센터(농산물종합가공센터) 기간제근로자를 다음과 같이 채용하고자 합니다. 1. 채용분야: 농산물종합가공센터 운영 2. 채용인원: 1명 3. 접수기간: 2024. 4. 18. ~ 4. 24. 4. 접수방법: 접수기간 내 방문접수(근무시간 내 09:00~18:00) 5. 접수장소: 농산물종합가공센터(연천군 연천읍 연천로42번길 80/031-839-4258) 붙임 2024년 농산물종합가공센터 기간제 근로자 채용공고 1부. 끝.
농업개발과 2024.04.18 -
2024년 2차 농업기술센터 친환경농업관리실 기간제 근로자 채용공고
2024년 친환경농업관리실 기간제근로자를 아래와 같이 채용하고자 합니다. 1. 채용목적: 친환경농업관리실 운영 2. 채용인원: 1명 3. 공고 및 접수기간: 2024. 4. 17. ~ 4. 22.(6일) 4. 공고방법: 연천군청 홈페이지 / 시험정보 게시판 5. 접수방법: 기간 내 방문접수(시간 9:00~18:00, 농업기술센터 친환경농업관리실) 6. 면접 및 합격자 선정: 2024. 4. 25.(목) (세부일정 개별통보) 7. 근무기간: 2024. 5. 1. ~ 2024. 12. 31. (예산소진 여부에 따라 가감 가능) 붙임 2024년 2차 친환경농업관리실 기간제 근로자 채용공고 1부. 끝.
농업개발과 2024.04.17 -
골목상권 상인회 매니저 모집 공고(재공고)
연천군 관내 골목상권 상인회의 상인조직 경쟁력 강화를 위해 전문성과 역량을 갖춘 매니저를 아래와 같이 모집합니다. 1. 모집대상: 연천군 골목상권 상인회에서 직무수행이 가능한 매니저 2. 모집인원: 골목상권 상인회(전곡첫머리거리상인회-전곡중앙상가번영회 연합) 매니저 1명 3. 신청기간: 2024. 4. 16.(화) ~ 4. 23.(화) 4. 제출서류: 주민등록초본, 신청서, 자기소개서, 경력기술서 등(공고문 첨부양식 참조) 5. 제출방법: 이메일 접수 ※ 자세한 사항은 붙임 공고문을 참고하시기 바랍니다. 붙임 골목상권 상인회 매니저 모집공고문(연천군). 끝.
지역경제과 2024.04.15 -
2024년 연천군 고대산 자연휴양림 단시간근로자(시설관리원) 채용계획 공고
1. 채용인원: 단시간근로자 2명 2. 공고 및 접수 기간: 2024. 04. 15(월). ~ 04. 26(금). 3. 근로기간: 2024.05.06. ~ 10.31.(약6개월) 4. 선발개요 가. 1차 서류전형: 응시자의 자격 적격성 검토(30%) 나. 2차 면접전형: 지원동기, 품행 및 성실성, 근로능력, 창의력 등 5. 합격통보: 2024. 05. 03. (금), 개별통보예정 붙임:. 모집공고문(안). 끝.
산림녹지과 2024.04.15
-